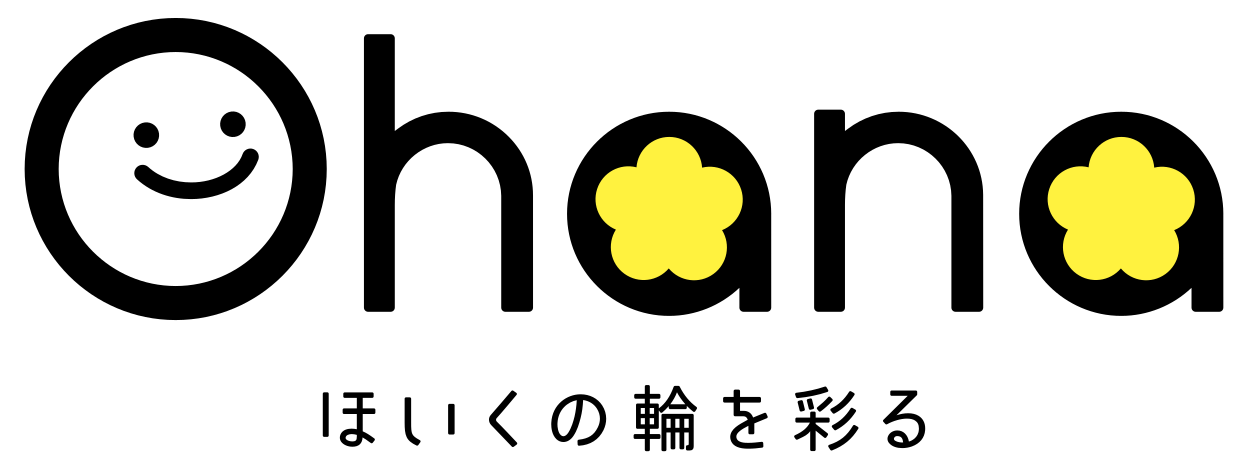2021.11.30

4歳児向けの遊びアイデア8選!おすすめポイントや注意点を解説
仲の良い特定の友達ができるようになる4歳児が行う遊びには、どのような特徴があるのでしょうか。
今回は遊びの特徴とねらいについて紹介するとともに、おすすめの遊びや注意点についても解説していきます。
4歳児向けの遊びの特徴やねらい
4歳になると遊びの場面で、友達と共通の目的を持って一緒に行うことが増えてきます。
例えば、砂場遊びでは山を作ってトンネルを掘るという目的を友達と共有し、協力しながら作ります。
また「〇〇ちゃんと一緒に遊びたい」という思いも芽生えるようになり、子どもにとっては遊ぶことが目的になる場合もあります。
また、どんどん体の動かし方が巧みになり、運動量も増えていきます。
3歳の頃は片足立ちしかできなかった子も、4歳になるとケンケンやスキップができるようになっていきます。
以下は、4歳児における遊びのねらいです。
● 特定の友達、気の合う友達と好きな遊びを楽しむ
● 目的やイメージを持って友達と遊び、社会性を養う
● さまざまな運動や遊びに挑戦し、体を動かす楽しさを味わう
● 友達とイメージを共有して遊ぶなかで、自分なりに表現しようとする
4歳児は、気の合う友達と好きな遊びをしたり、集団遊びを楽しみながら、社会性を身につけていきます。
好奇心が刺激される遊びを取り入れ、子どもの挑戦したい気持ちを育んでいきましょう。
4歳児におすすめの外遊びアイデア5選
まずは4歳児が楽しく運動できる外遊びのアイデアを紹介します。
子ども同士だけでなく、保育士と一緒にできる外遊びもあります。
4歳児におすすめの外遊び(1):けんけんぱ
片足跳びができるようになる4歳児の外遊びでは、みんなでけんけんぱをして運動遊びを楽しみましょう。
けんけんぱリングを地面に並べ、リングが1つのところは片足跳び、2つのところは両足を開いて着地します。
リングがないときは、代わりに細めのチューブやホースで手作りすることも可能です。
外遊びができる範囲にコンクリートの地面があれば、チョークで丸をたくさんかいて遊ぶこともできます。
ケンケンが苦手な子どもでも、友達が上手にケンケンする様子を見てまねしてやってみようと思うかもしれません。
4歳児におすすめの外遊び(2):だるまさんが転んだ
保育園での定番集団遊びの一つ、だるまさんが転んだを紹介します。
基本のルールに慣れてきたらアレンジしても楽しめるので、遊びを工夫したり発展させていきましょう。
【遊び方】
1. じゃんけんをして鬼を1人決めます。鬼は木や壁に向かって立ち、鬼以外の子達は鬼から離れたところに一列に並びます。
2. 鬼が「だるまさんが転んだ!」と言ってる間だけ子どもは鬼に近づき、鬼は言い終わるときに後ろを振り向きます。
3. 鬼以外の子どもはそのタイミングで止まります。
4. 動いてしまった子は鬼に捕まります。(鬼と手をつなぐ)
5. 何度か繰り返し行い、鬼までたどり着いた子どもは鬼に捕まっている子の手に触って「切った!」と言って逃げます。
6. 鬼にストップと言われたら子どもはその場で止まり、鬼は決められた歩数分移動して誰かにタッチできたら鬼を交代します。
だるまさんが転んだは、アレンジ版に「だるまさんの一日」というものがあります。
「だるまさんが歯磨きした」「だるまさんがダンスした」など、鬼がお題を考えて子どもがお題通りの動きをする遊びです。
4歳になると少し複雑なルールも理解できるようになりますので、ぜひ取り入れてみてください。
4歳児におすすめの外遊び(3):転がしドッジ
普通のドッジボールよりも簡単に行える転がしドッジを外遊びに取り入れてみましょう。
【遊び方】
1. 園庭に白線で大きな円を書き、コートを作ります。
2. 内野と外野を決めます。
3. 外野は内野に向けてボールを転がし、内野はボールに当たらないよう逃げ回ります。
4. ボールに当たってしまった子どもは外野に移動します。
5. 内野が最後の1人になったらその子どもがチャンピオンです。
ゲームがなかなか終わらない場合は制限時間を設け、残った子ども全員が勝利という形式にしても楽しめます。
人数が多いと逃げづらかったり子ども同士衝突しやすくなってしまうので、その場合はコートを2つ作りましょう。
4歳児におすすめの外遊び(4):かげふみ
晴れた日には外でかげふみを楽しみましょう。
ベースは鬼ごっこなのでルールも簡単です。
【遊び方】
1. じゃんけんをして鬼を決めます。
2. 鬼は他の子どもたちを追いかけ、タッチの代わりに影を踏みます。
3. 影を踏まれたら鬼を交代します。
大きな木の陰や建物の陰などに隠れて自分の影を消すことを考える子もいるでしょう。
「自分の影を消す場合は、そこに10秒しかいられない」など、新しいルールを作ってみてください。
4歳児におすすめの外遊び(5):ねことねずみ
ねことねずみは逃げることと追いかけること、一度にどちらも楽しめる集団遊びです。
【遊び方】
1. 園庭に2本の白線を引き、ネコとネズミチームに分かれてそれぞれ向き合って立ちます。
2. 保育士が「ネ、ネ、ネ……」と言ったら、お互い少しずつ近寄ります。
3. 保育士が「ネコ!」と言ったら、ネコチームはネズミチームを追いかけます。
4. 追いかけられる範囲を決めておき、タッチされた子どもは相手チームの仲間になります。
5. 何度か繰り返し、最後に人数が多いチームが勝利します。
「ネ、ネ、ネ……」の段階では、まだネコなのかネズミなのか分からないため、保育士の声にすぐ反応できる瞬発力が必要となります。
4歳児におすすめの室内遊びアイデア3選
続いて4歳児におすすめの室内遊びを紹介します。
4歳児におすすめの室内遊び(1):輪投げ
室内遊びでは、みんなで手作り輪投げゲームをして盛り上がりましょう。
【遊び方】
1. 新聞紙を細く丸めて繋げたものを輪投げのリングとして使用します。さまざまな大きさのリングを用意しておきましょう。
2. 輪投げのピンは、ペットボトルを使用します。倒れないよう水を入れておきます。
3. ペットボトルに点数を書いた紙を貼っておくと友達と競い合うことができます。
輪っかが小さいと入れるのが難しくなり、大きいと簡単になるなど大きさによって難易度が変わることが理解できます。
4歳児におすすめの室内遊び(2):ハンカチ落とし
ハンカチ落としは室内でできる集団遊びです。
遊びのルールを覚えながら、友達と関わる楽しさを味わいます。
【遊び方】
1. じゃんけんで鬼を1人決め、鬼以外の子どもたちは向き合って輪になって座り、手を後ろに回します。
2. 鬼は輪の周りを歩きながら、誰かの手のひらに気付かれないようにハンカチを落として輪を回るように逃げます。
3. ハンカチを落とされたことに気付いた子は鬼を追いかけます。
4. 逃げた鬼はハンカチを落とした人が座っていた場所に座ります。
5. 座ることができたら鬼を交代しますが、逃げきれずにタッチされたら続けて鬼をします。
ハンカチを落とされことに気付いた子どもはすぐに走り出す必要があるため、反射力が鍛えられます。
また「逃げるときは時計回り」「座ってる子どもは目をつぶる」などのルールを追加し、決まりを守って遊ぶ楽しさを感じてもらいましょう。
4歳児におすすめの室内遊び(3):制作遊び
4歳児はどんどん手先が器用になる時期なので、簡単な制作であれば1人でも作れるようになってきます。
イメージするものを自分なりに表現することを楽しむ4歳児には、制作遊びを取り入れていきましょう。
制作遊びは折り紙・粘土・お絵描きなど数多くのものがありますが、ここではカラフルな色合いが楽しい「マーブリング」を紹介します。
【必要なもの】
● 水
● マーブリング水溶液
● 絵の具
● 竹串
● 画用紙
【遊び方】
1. トレーなどの容器に水溶液を入れます。ない場合は洗濯のりでも代用できます。
2. 絵の具と水を混ぜ合わせて液状にします。あまり濃すぎると沈んでしまうので調整してください。
3. トレーにさまざまな色の絵の具を垂らして模様にします。
4. 竹串で軽く混ぜると、個性的な模様に仕上がります。
5. 白の画用紙をトレーの上にそっと乗せ、模様を移します。
6. 画用紙が乾いたら完成です。
マーブリングした紙を、好きな形に切り取って画用紙に貼り付けても楽しいでしょう。
どんな模様が出来上がるか予想できないマーブリングは、子どもの想像力を養います。
4歳児の外遊び・室内遊びで注意すること
4歳児の遊びで保育士が注意するべき点を解説します。
運動が苦手な子に配慮する
4歳児は運動機能が発達し、体を動かす外遊びが楽しくなる年齢です。
しかし、みんながみんな運動が得意なわけれはありません。
なかには運動が苦手で、思うように体が動かせない子もいます。
上手に遊ぶ友達の姿を見て動きをイメージしたりしますが、保育士が励ましの声かけをしたり、個別にやり方を教えてあげることも大切です。
4歳になると集団でゲーム性のある遊びを行うことも増えてきますので、特にチーム戦のときは注意が必要です。
「〇〇ちゃんのせいで負けた」という空気にならないよう、みんなで楽しく遊べる方法をクラス全体で考えたり、意見を出し合う場を作りましょう。
子ども同士のケンカに注意
4歳程になると言葉で自分の気持ちを伝えることが上手になるため、ケンカにおいても友達同士で解決できることが増えてきます。
また、思いやりも芽生えてくるので、ケンカしている子どもの仲裁に入ろうとする子もいるかもしれません。
ですが、ケンカの内容によっては保育士が止めに入らなければならないものもありますので注意してください。
ケガをする恐れがあるとき、1人の子どもが複数の子どもに責められているとき、子どもが保育士に助けを求めているときなどです。
保育士がケンカの仲裁に入るときは、双方の言い分をよく聞く必要があります。
どちらか一方を悪者にして謝罪を要求したり、子どもの話を全く聞かずに無理やり解決させてしまうと、分かってもらえなかった悔しさだけが残ってしまいます。
保育士は双方の気持ちに共感し、子どもの気持ちに寄り添うことが大切です。
「〇〇ちゃんは〇〇くんにどうしてほしかったのかな?」「こういうときはどうしたらいいと思う?」と、子ども自身が考えられるような声かけをしましょう。
4歳児の遊びは友達との関わりや表現を楽しめるものを用意しよう
4歳児向けのおすすめ遊びアイデアを紹介しました。
遊びの特徴やねらいを踏まえて、子どもの発達に即した遊びを楽しみながら行っていくことが大切です。
周りの友達と一緒に取り組みながらも、自分の好きなことを追求できる環境は、子どもの健やかな成長を促進させていくでしょう。
▼この記事を読んだ方におすすめの記事はこちら
・【若手保育士さん必見! 】これを読めば指導案が簡単に書けちゃう!?
・保育日誌の書き方のポイント!年齢別の例文も
・保育園で4歳児クラスの担任になったら?
▼4歳児におすすめの絵本はこちら
記事公開日:2021.11.30
記事更新日:2021.11.30