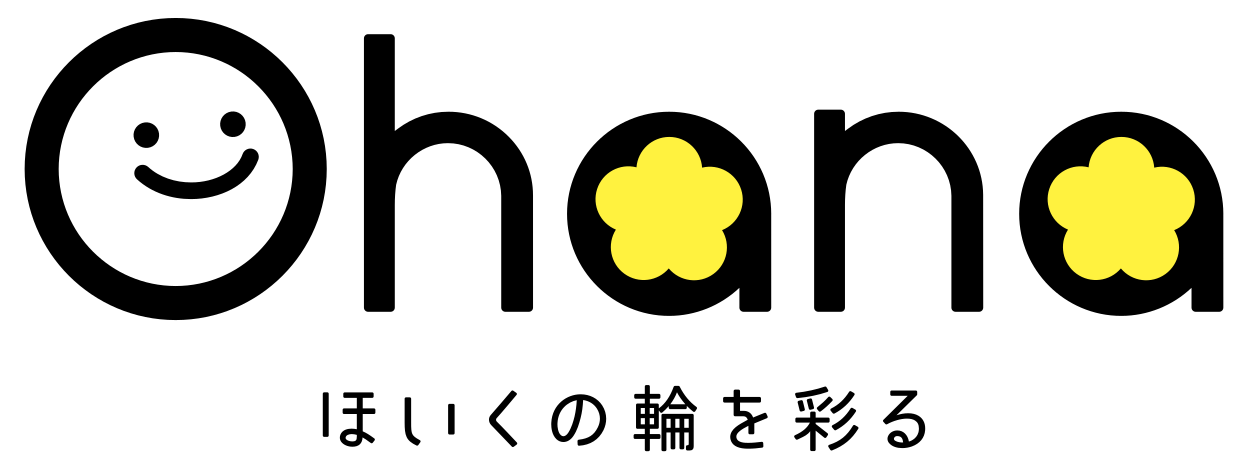2019.05.30

保育士の負担軽減につながる?配置基準を取り巻く課題とは
保育園の規模の大小にかかわらず、子どもたちの保育環境を一定にするため、国では「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」を設けています。
ここでは子ども1人当たりの広さや、保育士1人で保育することができる人数「配置基準」を定めています。
現在、政府はこの「配置基準」を緩和することで、受け入れる子どもの人数を増やすことを検討しています。
では、そもそもこの配置基準とはどのようなものなのでしょうか?今回は保育士の配置基準と今後の課題についてご紹介します。
保育士の配置基準とは
国が定めている配置基準では、保育士の人数はどのように決まっているのでしょうか?
「0歳児3人に対して、保育士1人」が基本
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の第33条2項では、子どもの年齢ごとに保育士1人で保育できる人数を以下のように定めています。
“保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上とする。ただし、保育所一につき2人を下ることはできない。”
つまり、保育士1人で保育できる人数は、次の通りになります。
・乳児(0歳児)なら3人
・1歳~3歳なら6人
・3歳~4歳なら20人
・4歳以上なら30人
この基準通りの保育士の配置では、子どもの安全を確保するためには保育士は片時も目が離せない状態となり、保育士の負担はとても大きくなります。
そのため、公立の保育園や認可保育園では、保育士の人数を基準よりも増やし、対応しているところもあります。
無認可保育園では?
公立や認可保育園では国が定めた配置基準をクリアすることが求められていますが、無認可保育園ではどのような配置基準になっているのでしょうか。
さらに1人の保育士が担当する人数が多い!?
無認可保育園では、この配置基準を守らなければならないという決まりはありません。
そのため、保育士1人で0歳児を5人保育していたとしても、法的な問題がないため、保育士の配置基準は甘くなりがちです。
ただし無認可保育園であっても、保育士の人数は基準以上を満たしているものの「園庭がないから」「広さが足りないから」などの理由で、認可保育園にならずに運営していることもあります。
一概に「無認可保育園だから、保育士1人が担当する子どもの人数が多い」とは言えませんので注意が必要です。
配置基準の緩和案とは
現在、待機児童解消のために保育士の確保が進められています。
しかし確保が思うように進んでいないことや財政面での影響から、政府はこの配置基準の緩和案を検討しています。
朝夕の保育士の最低人数の緩和
本来、開園時間中は最低保育士を2名以上配置する必要がありますが、保育士の確保が難しい地域ではかなりの負担となっています。
そのため、厚生労働省は、これらの地域の限定措置として、朝夕の時間帯のみは保育士1人と無資格者で対応することを認める方針を出しています。
2015年度のみの限定措置としてスタートしていますが、2016年度も延長して行う方向で検討されています。
年齢によって、幼稚園教諭や小学校教諭も保育OK
2016年度からの緩和案として、子どもの年齢によって保育士以外の有資格者を活用することが検討されています。
3歳から5歳までは幼稚園教諭、5歳以上には小学校教諭が保育士に代わって保育可能となります。
また、養護教諭については、看護師と同等の扱いとして保育する年齢の制限は定めず、どの年齢の子どもの保育でも可能としています。
この緩和案では、保育士全体の3分の1を超えないような人数にする制限は設けているものの、保育士以外の有資格者を活用することで、受け入れられる子どもの人数を増やす目的があります。
まとめ
子どもの安全を守るためには、保育の質を低下させるような事態だけは避けなければなりません。
緩和案について協議している「保育士等確保対策検討会」においても、保育士の人数の緩和策だけでなく、保育士そのものの待遇改善や地位向上を図ることも必要だとする意見が、日本保育協会や全国私立保育園などから出ています。
第一線で働く保育士の方は、今後も注目するべきテーマになるでしょう。
▼おすすめ記事
- 保育士必見!明日から使えるおすすめ手遊びをシーンごとに紹介
https://ohana.hoiku-hiroba.com/post/692 - 誕生会の出し物ってどんなことをやったらいいの?
https://ohana.hoiku-hiroba.com/post/715 - 保育日誌の書き方のポイント!年齢別の例文も
https://ohana.hoiku-hiroba.com/post/332
記事公開日:2019.05.30
記事更新日:2021.07.15